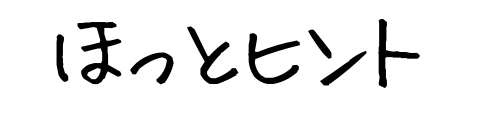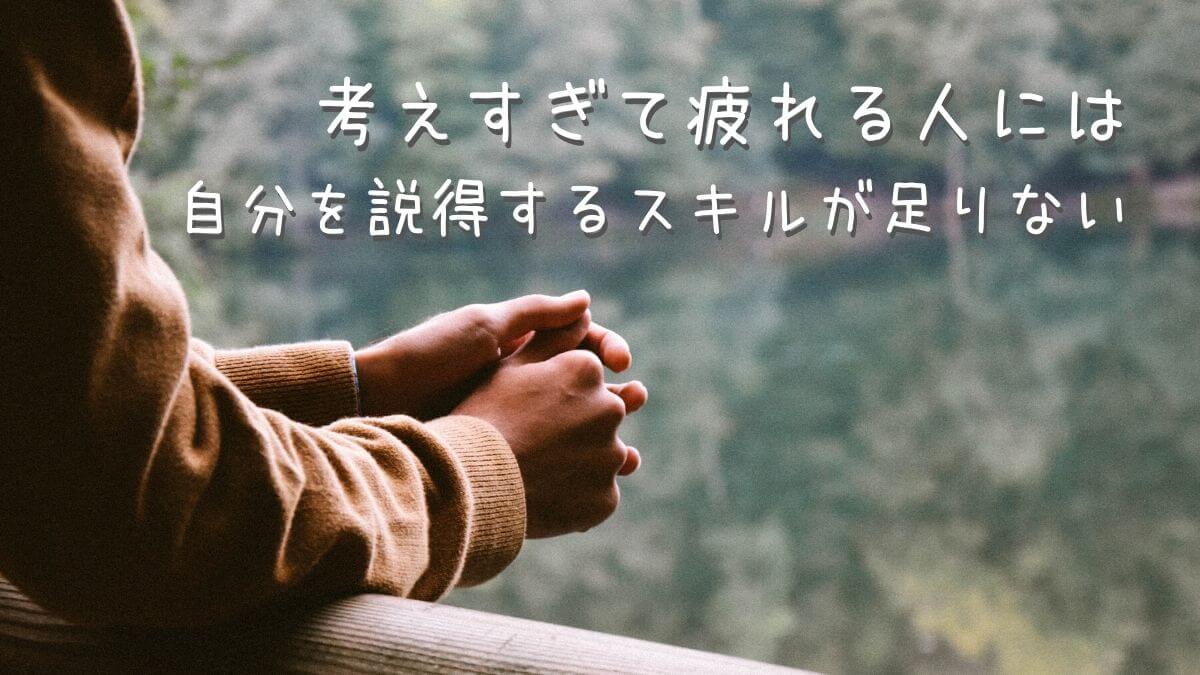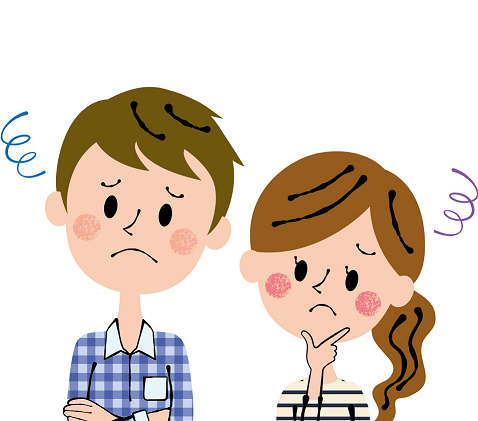
「人と接するたびに、色々と深く考えすぎて疲れてしまう」
「不安な気持ちが強くなると、頭の中で考え込んで抜け出せなくなる」
何事も考え込んで答えを出そうとして疲れ果ててしまい、もうイヤになることってありますよね。
本記事では、考えすぎて疲れてしまうと悩んでいる方へ、その緩和方法について解説していきます。
考えすぎて疲れる人に足りないものは、自分を説得するスキル
結論から言うと、この自分を説得するスキルとは2つあります。
- 自分の考えの根拠を見つけるスキル
- 自分の考えとは正反対の事実を探すスキル
これらは認知行動療法という、うつ症状の改善のためにも用いられる手法の1つなんです。
たとえば、
仕事で細かいことだけど、分からないことがあったとき、
- こんな小さなことを上司にいちいち確認したら、出来の悪い人だと思われるかも
- 上司に確認せずに、それがミスになった場合、もっと信用を失うかも
この2つの考えを行ったり来たりしてしまうと、疲れてしまいますよね。
しかしここで、
- その考えの根拠は何か
- その考えの正反対の考えを挙げるとしたら、どんなものがあるか
こうしたことを考えてみるんです。
すると、
- 分からないことを聞いて、上司が自分のことを出来の悪い人だと思う根拠は…特に見つからない
- 逆に小さなことでも確認することで、報連相がきちんと出来る人だと評価される可能性もあるかも
こんな風に考えることもできますよね。
そして、このスキルを自然と身に付けていくためには、そもそも自分がなぜ考えすぎて疲れるのか、その原因を掘り下げていく必要があるんです。
考えすぎて疲れる根本的な理由
何事にも考えすぎてしまう人は、以下の特徴を持っている可能性があるんです。
- 自分を苦しめる「考え方のクセ」を持っている
- 心の底に無力感に対する強い不安がある
考えすぎて疲れるのは、性格だから変えられないと思っている方もいるかもしれません。
しかし自分自身と向き合い、スキルを身に付けていくことで、考えすぎて疲れてしまう状態は少しずつ緩和させていけるものなんです。
1.自分を苦しめる「考え方のクセ」を持っている
人は誰しも、物事の捉え方や考え方にクセがあります。
しかし人によっては極端な考え方をしてしまい、無意識に自分を苦しめている場合があるんです。
たとえば、
相手はこう思っているに違いないとすぐに決めつけてしまいがち
この考え方のクセを持っていると、他人のちょっとした不機嫌な表情を「自分を嫌っているからだ」と決め付けてしまいやすくなります。
>>>「私、嫌われているかも」と悩むのは、自他境界の曖昧さが原因!?
また、
他人のことを「自分を好いている」か「自分を嫌っている」かのどちらか一方で考えてしまいがち
このようなクセを持っている場合は、他人のことをある意味で、
「敵」か「味方」か
でしか見られなくなり、人付き合いがとても苦しいものになりやすかったりします。
そしてこの心理には、スプリッティングという心の働きが大きく関係しているんです。
>>>スプリッティング(分裂)とは?葛藤から自分を守る心理について
ここまで見てきた考え方のクセを自分が持っていることに気付けないと、考えすぎて疲れる状態になったとき、
- その考えの根拠は何か
- その考えの反対の考えを挙げるとしたらどんなものか
これらの考えが浮かびにくくなるんです。
そして、こうした考え方のクセが強いと、目の前で起こる出来事を極端に解釈してしまいやすくなります。
すると、
- 「あの人に嫌われたに違いない」
- 「仕事をミスした自分は、ダメな存在だ」
といったように、心にショックな出来事が多くなってしまいます。
そうなると、同じ出来事を何度も頭の中で繰り返してしまう「反すう(ぐるぐる)思考」にも陥りやすくなるんです。
2.心の底に無力感に対する強い不安がある
考えすぎて疲れてしまう理由の根底には、そもそも強い不安感があることが多いです。
それはもちろん失敗することへの不安もありますが、それよりも強い不安の元が考えられます。
それは無力感です。
無力感とは、「自分には何も成し遂げる力はない」と感じてしまう感覚です。
この「無力感」と「考えすぎて疲れること」がどう関係しているかというと、過去に、
「自分は何をしても上手くいかず、無力感に押しつぶされてしまった」
という経験が関係しています。
その無力感に押しつぶされてしまった経験とは、ダブルバインドと呼ばれるものです。
ダブルバインドとは、モラルハラスメントの一種で、
何をしても不快な気持ちになるコミュニケーションのことです。
>>>ダブルバインドとモラハラは密接な関係!その事例と対処方法
たとえば新しい仕事で分からないことがあった場合、
- 上司に確認すると「いちいち確認するな」と怒られる
→不快な気持ちになる - 確認せずに進めると「勝手に進めるな」と怒られる
→不快な気持ちになる - 生活もあるから今すぐには退職できない
→逃げる選択肢がない
このように、ダブルバインドをされると、置かれた環境から逃げることもできず、何をしても不快になって無力感を抱きやすくなるんです。
このようにダブルバインドへの恐怖心があると、何か行動したり発言したりする前に
「無力感に押しつぶされないよう、徹底的にリスクを考えておこう」とします。
その結果として、考えすぎて疲れるほどになってしまうんです。
考えすぎて疲れる心理の裏には、こうした恐怖心があるわけです。
スポンサーリンク
考えすぎて疲れる人は、現実を見れていないから辛くなってしまう
考えすぎて疲れる人に有効なスキルは、
- 自分の考えの根拠を考える
- 自分の考えとは正反対の事実を考える
というものでしたね。
このスキルが身についてくると、あることに気付き始めます。それは、
自分が想像していた心配事や不安は、ほとんど自分の想像だった
ということです。
自分のネガティブな考えの根拠を考え、さらにその考えとは正反対の事実を考え続けられると、
「想像していた不安は、実際には起こらない」
そう少しずつ思えてくるはずです。
自分の考えの根拠や正反対の事実を考える上でのコツを、こちらの記事でも紹介していますので、ぜひ一読して身に付けてほしいと思います。