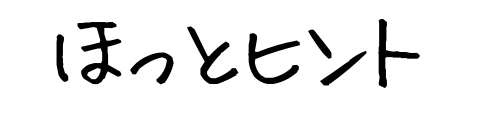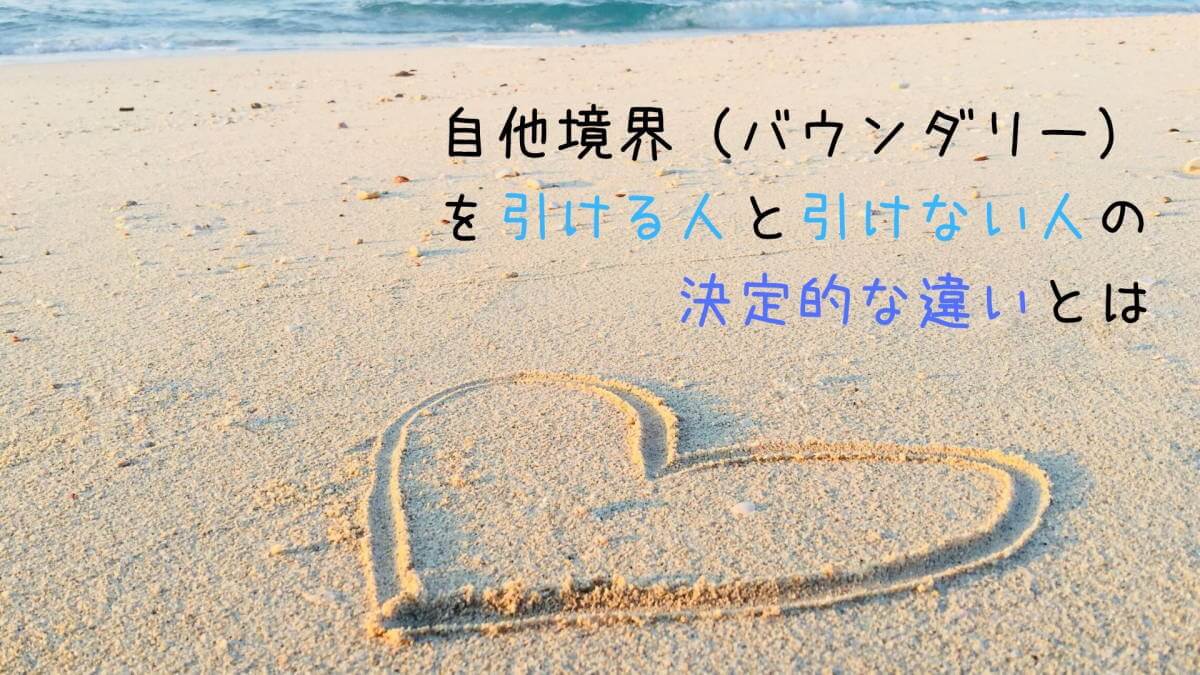- 「なぜ自分は自他境界を引けないのだろう」
- 「自他境界を引けている人は自分と何が違うのだろう」
自他境界を引くことが重要だとは理解できても、実際にどうすればいいのか、なかなか分かりずらいですよね。
本記事では、自他境界を引けるようになるために必要なことについて解説していきます。
自他境界(バウンダリー)を引ける人と引けない人の決定的な違いとは
それは、
人間関係を基本的にどのように捉えているか
という点です。
自他境界を上手く引ける人の多くは、人間関係を「共生関係」と捉えています。
共生関係とは、
- 辛い時には辛い感情を共有し合える
- たとえ間違っても許し合える
- お互いに違う意見や気持ちでも、認め合える
共生関係では、お互いに相手のことを、自分とは異なる一人の人間として尊重し合えます。
しかし、自他境界を上手く引けない人は、人間関係を「主従関係」と捉えている傾向が強いようです。
主従関係とは、
- 上の人間の意に沿わなければ、罰を受ける
- 上の人間の意向には絶対に従わなければならない
- 下の人間は、上の人間に都合の悪い意見や気持ちを持ってはいけない
主従関係の特徴は、物理的にも精神的にも、一方が従う側に徹する関係だということです。
では、人間関係を「主従関係」と捉えてしまう理由は、何なのでしょうか。
親との関係が「共生」か「主従」かで、その後の人間関係のスタンスが決まる
人間関係が主従関係に陥ってしまう理由には、生まれて初めての人間との関わりである、親との関係が大きく影響しています。
親が子供に対して、主従関係で接する場合、
親との間で共生関係を体験できなかった人は、共生関係という関わり合いの存在を知らないまま成長していきます。
それによる大きな弊害の一つは、
目上の人以外のフラットな関係の人(友人、知人など)に対して、「対等」な感覚が得られない
ということです。
それにより、
- 他者に対して遠慮気味になる
- 自己主張することに抵抗を感じる
このようになりやすくなります。
関連記事「「人付き合いが疲れる…」その気持ちの根底には〇〇がある」
主従関係では、自他境界を引くことを許されない
親と主従関係の中では、基本的に子供は自他境界を引くことを許されません。
そのため、たとえば親が不機嫌になった時、その感情が
- 自分の感情なのか
- 親の感情なのか
の区別をつけられなくなる傾向があります。
そのため、親が不機嫌になると、子供である自分の中に不快な感情を感じてしまいやすくなります。
そして、その親の不機嫌を
「自分が何とかしなければ、自分の中の不快感を消すことが出来ない」
と感じてしまい、親の感情の責任を負おうとするわけです。
関連記事「「私、嫌われているかも」と悩むのは、自他境界の曖昧さが原因!?」
スポンサーリンク
自他境界を引けない人が持っていない重要スキル
では、自他境界を引けるようになるためには、どうすればよいのでしょうか。
ヘンリー・クラウド著「境界線(バウンダリーズ)」では、自他境界が曖昧な人が子供時代に身に付けてこなかったスキルとして、5つを挙げています。
- 限界を設けるスキル
- 助けを求めるスキル
- 自分の価値や感情、ニーズを確認するスキル
- 適切に感情を表現するスキル
- ノーを言うスキル
自他境界を明確にしていくためには、この5つのスキルを身に付けていくことで、自分を守っていけるようになるはずです。
しかし、これら5つのスキルをすぐに身に付けるのって難しいですよね。
この5つの中でも、本記事で注目するのは「限界を設けるスキル」です。
この「限界を設けるスキル」とは、
自分の体力や精神力が、どこまでなら正常を保ったままでいられるのかというラインを引くスキル
と言えるものです。
自他境界が曖昧だと、自分の限界を引く基準を
「自分自身の体力、体調・精神力」
ではなく、
「会社や上司が求める労働時間、仕事量」
という現実の自分を無視したモノサシを基準にしてしまう傾向が強くなってしまいます。
その結果、
- 身体が壊れるまで働いてしまう
- 辛くても耐え続けて、ストレスでメンタルを崩してしまう
など、社会生活を送る中で自分を守り切れなくなるわけです。
そうならないためにも、限界を設けるスキルは重要になってきます。
しかし、これまで生きづらさに苦しんできた人ほど、いきなりそんなスキルを身に付けることはとても難しいものです。
だからこそ少しずつでいいんです。まずは、
自分はこれまで「限界を設けるスキル」を持てていなかったんだ
そう気付けることが、自分を変える大きな一歩になるんです。