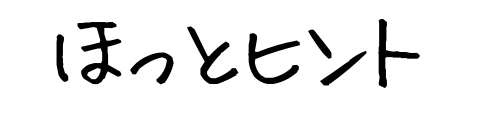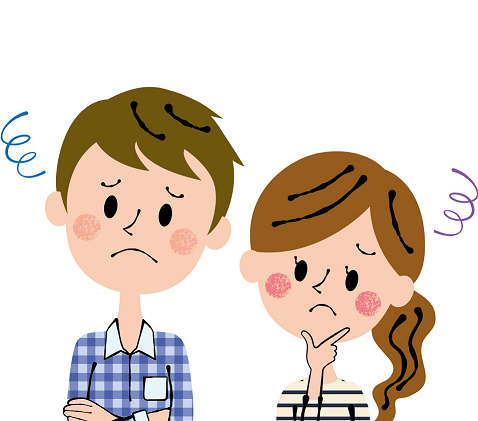
「失業や離婚によって、自分に全く自信が持てなくなってしまった」
「アイデンティティクライシスとはどのような心理状態なのか知りたい」
自分のアイデンティティを見失ってしまうことは、その言葉以上に精神的に辛く苦しいものです。
そして、その苦しさは想像以上に根深い問題でもあるんです。
本記事ではアイデンティティクライシスの本質とその乗り越え方について解説していきます。
アイデンティティクライシスの本質は「ありのままの自分の否定」
アイデンティティクライシスとは簡単に言うと、存在価値があると思っていた自分を見失ってしまうことです。
たとえば、
- 〇〇会社に勤めている自分にこそ価値がある
- 誰かの役に立てる自分にこそ価値がある
- 若い自分・元気な自分にこそ価値がある
- 家庭を持っている自分にこそ価値がある
アイデンティティクライシスは、このような自分が価値を感じているアイデンティティを何かをキッカケに失ってしまうことで生じるものです。
>>>自分のアイデンティティとは?|その意味と種類をわかりやすく解説!
そして、そもそもアイデンティティクライシスに陥りやすい人は
自分独自の価値観がなく、いつも他人の基準や価値観を重視して生きている
という特徴があります。
つまり、元々コアとなる自分のアイデンティティが確立されていない可能性があるんです。
もともとコアとなるアイデンティティを持てていない可能性
アイデンティティには大きく2つの側面があります。
- 社会的なステータスや役割など「自分の外側の存在価値」
- 生まれつきの性格や能力といった「自分の内側の存在価値」
このうち自分の内側の存在価値というものが「コアとなる自分のアイデンティティ」になります。
そしてこれは、ありのままの自分のことでもあるわけです。
この自分のコアとなるアイデンティティが確立されていない場合、失業や離婚などによって自分の外側の存在価値を失うと、大きなアイデンティティクライシスを起こしやすい傾向があります。
では、なぜ元々ありのままの自分に価値を感じられず、コアとなるアイデンティティを持てていないのか。
それは同じくコアとなるアイデンティティを持てていない親との関係性にあります。
アイデンティティと親との深い関係性
そもそも自分の存在価値に自信がない親は、子供を自分の心の支えにしようとしがちです。
そうした親は子供が精神的に自立することを受け入れられません。
子供が自分独自のものの感じ方や価値観、意志を持つことを認めず、親の感じ方や価値観と違うところがあれば、それを親への反抗・裏切りと見なしてしまいます。
これには自他境界という心の境界線の問題が関わってきます。
>>>「私、嫌われているかも」と悩むのは、自他境界の曖昧さが原因!?
そうして育てられた子供は、
- ありのままの自分では受け入れてもらえないと感じる
- 親の機嫌によって自分の存在価値がゆらぐため、いつも混乱する
- 自分は何をどう感じていいのか分からなくなる
こうして自分の存在自体に確信が持てなくなり、コアとなるアイデンティティを確立できないまま大人になってしまいます。
八方美人や見捨てられ不安との深い関係性
自分の存在自体に確信が持てないと、人は自分のアイデンティティを「外側にあるもの」に依存しがちになります。
たとえば、
アイデンティティクライシスに苦しんでしまう人は、ある意味で
生まれてから一度も誰からもありのままの自分を受け入れてもらえなかった
という辛さや悲しみを心の底では感じているとも言えるんです。
アイデンティティクライシスの乗り越え方
辛く苦しいアイデンティティクライシスを乗り越える方法は大きく2つあります。
- コンプレックスから新たなアイデンティティをつくる
- 役割的なアイデンティティではなく、能力的なアイデンティティを探す
1.コンプレックスから新たなアイデンティティをつくる
誰でも1つや2つ、コンプレックスというものを持っているものです。
- 周りと比べて自分だけが独身だ
- 他人に気を遣いすぎてしまう性格がイヤだ
そして、こうした自分がコンプレックスだと思っていることほど、それは自分を自分たらしめているものだとも言えますよね。
それでもコンプレックスであれば、誰もがそれを自分のアイデンティティだとは認めたくないと思うものです。
しかし、コンプレックスは見方を変えれば立派な自分のアイデンティティを補強するものにもなります。
コンプレックスは見方や環境を変えれば変わるもの
物事には必ず裏と表があるように、コンプレックスも裏を返せば良い面だと捉えることができるものです。
- 「周りと比べて自分だけが独身だ」
→独身であることの悩みをブログで発信したら、多くの共感を得て頼られるようになった - 「他人に気を遣いすぎてしまう性格がイヤだ」
→よく思い出すと、これまで他人に気を遣う姿勢を褒めてくれた人が何人もいた
これらの例は小さなことに感じるかもしれません。
しかし、こうした小さな自己肯定を心の底から納得して受け入れていく一歩が、アイデンティティクライシスを乗り越えていくためには大切なんです。
そして結局のところ、自分は何者かというのは限られた自分の周りの人との比較によるところが大きいんです。
- 日本に住んでいれば、自分は日本人だとは意識しないが、アメリカに住んでいれば、日本人であることがアイデンティティになる
- 自分の周囲の人(家族、友人、同僚)の多くが東大卒だったら、自分が東大卒でもそれはアイデンティティにならないかもしれない
環境を変えることで見えてくるアイデンティティは必ずあるものです。
2.役割的なアイデンティティではなく、能力的なアイデンティティを探す
アイデンティティには見方によっていくつかの種類があります。
- 社会的アイデンティティ
(学歴、出身地、所属組織、) - 役割的アイデンティティ
(役職、親、上司、後輩、妻、) - 年齢的アイデンティティ
(若者、アラサー、) - 能力的アイデンティティ
(仕事が早い自分、〇〇という特技がある自分、)
そして、この中でも社会的アイデンティティや役割的アイデンティティは外部の環境の変化によって見失いやすい特徴があるんです。
>>>自分のアイデンティティとは?|その本質をわかりやすく解説!
スポンサーリンク
アイデンティティクライシスは今に始まったことではない
他人と接することに漠然とした不安や恐怖心がある場合、その原因の大元には
「ありのままの自分ではダメなんだ」という無意識の自己否定
が隠れている可能性があります。
それはつまり、
- 自分は何者なのか
- 自分は何者になれば愛されるのか
という悩みを生まれたときからずっと抱え続けて、アイデンティティクライシスを起こしていたとも言えるわけです。
そして成長するにあたり、
- 勉強できる自分になれたら価値がある
- 他人から見て「いい人」である自分になれたら価値がある
このようにありのままの自分を否定しながら、自分以外の自分になろうと人一倍頑張り続けてきたのではないでしょうか。
つまり、本当の意味でアイデンティティクライシスを乗り越えるために必要なことは、自分だけの価値観や意志を少しずつ少しずつ確立させていくことなんです。
そのためには、
- 自分は自他境界があいまいなのかもしれない
- 見捨てられ不安が生じる理由
これらのことに気付いていくことがその近道となるはずです。